新しい小津安二郎にふれる
『小津安二郎大全』刊行記念シンポジウム
2020年1月18日(土)早稲田大学小野記念講堂
タイムスケジュール
14:00 開場
14:30-15:20 シンポジウム 石井妙子、舩橋淳、小沼純一、志村三代子
15:30-16:00 「私のベレット」上映(脚本監修:小津安二郎、企画編集委員:中平康、山本嘉次郎、野村芳太郎、千葉泰樹、関川秀雄、五所平之助、滝沢英輔、小石栄一、牛原虚彦、松林宗恵、田中重雄 監督:大島渚)
16:10-16:40 トーク 望月智充
16:50-17:40 トーク 周防正行 利き手 宮本明子・松浦莞二
17:40-18:10 サイン会 望月智充・周防正行

「アルバム小津安二郎1903‐1963永遠の映画」(1‐8頁)
小津安二郎「ここは楢山 母を語る」(9頁)
蓮實重彦「小津安二郎」(10‐15頁)
辻原登「小津徒然」(16‐17頁)
中村博男「小津安二郎と伊勢の「味」 代用教員時代の小津の落書き」(18‐19頁)
笠智衆「わが師の恩 親父が子を育てるように仕込んでくれた小津監督」(20‐21頁)
青木富夫インタヴュー(聞き手=篠崎誠)「突貫小僧、小津先生と蒲田を語る。」(22‐34頁)
牛原虚彦「『おっちゃん』が貫いた“豆腐の味” 心残りな小津安二郎監督の死」(35‐37頁)
オスカー・シスゴール「九時から九時まで 『その夜の妻』原作小説」(38‐48頁)
宮川一夫「たった一度 小津安二郎監督と『浮草』」(50‐53頁)
斎藤武市インタヴュー(聞き手=田中眞澄)「小津組助監督修行」(54‐69頁)
小津安二郎「映画女優の場合」(70‐73頁)
黒沢清・青山真治 特別対談「なぜ小津安二郎なのか 小津マネはしたけれど」(74‐87頁)
澤登翠「小津作品の弁士をつとめて」(88‐89頁)
関正インタヴュー(聞き手=田中眞澄)「ジュロン抑留所の想い出 ガリ版新聞文化部長・小津安二郎」(90‐99頁)
「『お早よう』オープンセット写真」(100‐101頁)
小津安二郎「今後の日本映画 戦後第一声」(102‐105頁)
田中眞澄「浅原六朗、または一九三〇年という《場》」(106‐111頁)
吉田喜重・岡田茉莉子・前田英樹 鼎談「不思議な監督 小津安二郎の『映画とはドラマだ、アクシデントではない』という言葉をめぐって」(112‐130頁)
田中英司「『東京画』イミテーションの誘惑」(131‐133頁)
桜むつ子インタヴュー(聞き手=田中眞澄)「バーのマダムと飲み屋の女将」(136‐142頁)
川崎長太郎「淡雪」(143‐149頁)
川崎長太郎「恋敵小津安二郎」(150‐155頁)
小津安二郎原作・八木保太郎脚色「愉しき哉保吉君」(156‐187頁)
山内静夫インタヴュー(聞き手=諸富隆子)「小津組の小道具について」(190‐195頁)
広津和郎「父と娘 『晩春』原作小説」(196‐209頁)
武田麟太郎「雪もよい モデル小説」(210‐221頁)
ジョジアーヌ・ピノン(川竹英克訳)「オズの国への旅 小津安二郎、一九三〇年代の日記」(222‐229頁)
小津安二郎・八木保太郎・柳井隆雄「父ありき(第一稿)」(230‐254頁)
<増補>
小津安二郎「小津安二郎(全)俳句 二百二十三句」(255-262頁)
松岡ひでたか「小津安二郎と俳句」(263-267頁)
高峰秀子「三度、心が震える」(268-269頁)
平山周吉「昭和史の中で小津映画を観れば」(270-273頁)
蓮實重彦「”神話”を引きはがした『監督小津安二郎』」(274-275頁)
蓮實重彦「無声映画のスター・井上雪子さんを悼む」(276-277頁)
蓮實重彦(聞き手 伊藤洋司)「原節子と日本の名女優 追悼・原節子」(278-290頁)
「小津安二郎略年譜」(291頁)
「小津安二郎フィルモグラフィー(内容解説=関口良一)」(292‐299頁)

「余計なお世話-序にかえて-」(1頁)
「第一部 小津安二郎の俳句とその周辺」(9-11頁)
「一 一九三三(昭和八)年(三一歳)」(11-32頁)
「二 一九三四(昭和九)年(三二歳)」(32-54頁)
「三 一九三五(昭和十)年(三三歳)」(54-113頁)
「四 一九三七(昭和十二)年(三五歳)」(113-116頁)
「五 一九三九(昭和十四)年(三七歳)」(116-130頁)
「六 一九五四(昭和二九)年(五二歳)」(130頁)
「七 一九五九(昭和三四)年(五七歳)」(131-134頁)
「八 一九六〇(昭和三五)年(五八歳)」(134-137頁)
「九 一九六一(昭和三六)年(五九歳)」(137-141頁)
「第二部 小津安二郎と俳句」(143-
「一 酒」(144-148頁)
「二 寺田寅彦の映画論の影響」(148-152頁)
「附録 「文学覚書」」(153-169頁)
「おわりに」(170-171頁)
「新版 あとがき」(172-173頁)
「小津安二郎(全)俳句 二百二十三句」(174-190頁)
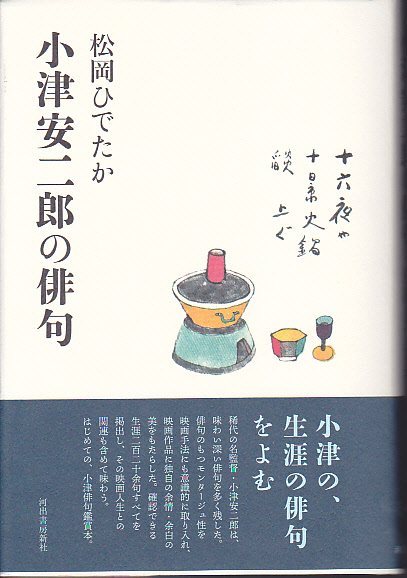
「まえがき」に代えて(15-31頁)
「第一部 『東京の合唱』(33-159頁)
「第二部 『生まれてはみたけれどー大人の見る絵本』」(161-317頁)
「参考文献」(319-327頁)
「参考映像」(328頁)
「あとがき」(329-333頁)
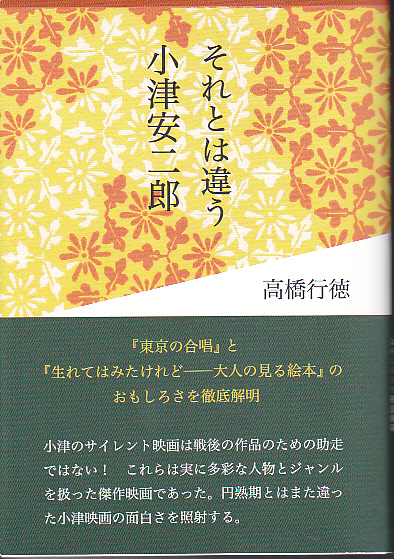
平山周吉「小津安二郎 第一章 「無」と「無常」と「無藝荘」」(112-120頁)
※冒頭を引用する。
「毎年、十二月十二日に、北鎌倉で小津会が開かれる。映画監督の小津安二郎が御茶ノ水の東京医科歯科大学付属病院で亡くなったのは、昭和三十八年(一九六三)十二月十二日だった。その日は、小津の満六十歳の誕生日だったから、律儀にもきっちり六十年の生涯だったことになる。映画製作においても日常生活においても、何事をもゆるがせにしない小津は、図ったわけではないのに還暦の年の誕生日にこの世を辞した。」(112頁)
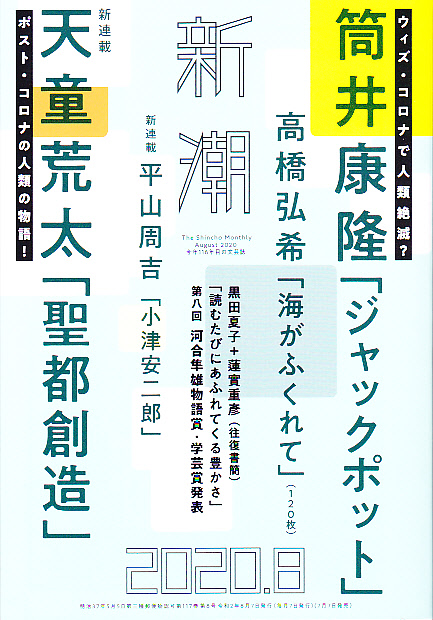
平山周吉「小津安二郎 第二回 第二章 和田金と宣長と「東京物語」の松阪」(180-188頁)
※冒頭を引用する。
「一九〇一(明治三十四年) 昭和天皇
一九〇二(明治三十五年) 小林秀雄
一九〇三(明治三十六年) 小津安二郎
一九〇四(明治三十七年) 笠智衆
一九〇五(明治三十八年) 厚田雄春
小津を中心軸に据えて、二十世紀初頭の日本に生を受けた人々を毎年一人ずつピックアップしてみたのが右の小年表である。笠智衆は小津の”分身”であり、小津映画を代表する役者である。厚田雄春は「キャメラ番」を自称した小津組スタッフである。二人ともヴィム・ヴェンダース監督の「東京画」に出演し、小津の名前が題名に入った著書も遺した。いつまでも小津神話の生ける語り手である。」(180頁)
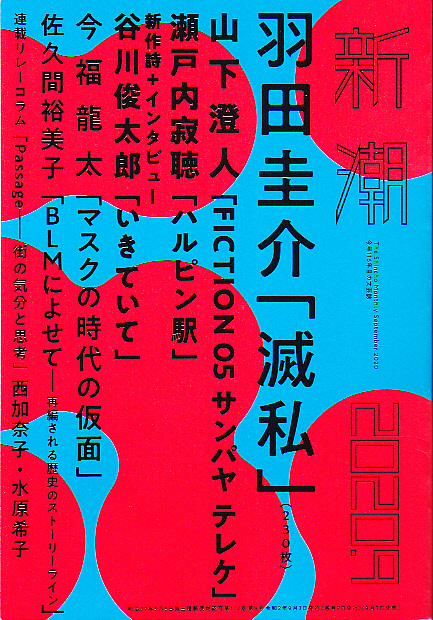
平山周吉「小津安二郎 第三回 第三章 「麦秋」の不可思議なキャメラ移動」(132-141頁)
※冒頭を引用する。
「円覚寺の「無」のお墓から始まったせいか、東慶寺にある小林秀雄の墓と、お墓の話題が続いてしまった。このまま続けるなら、「宗方姉妹」の田中絹代・山村聰夫妻と妹の高峰秀子が住む大森の家近くの猫のいる墓地だとか、「小早川家の秋」のラスト、火葬場近くにある石仏にカラスが我が物顔で乗っかった、「枯枝に烏のとまりたるや秋の暮」の芭蕉を俳諧化したような映像に進むのが自然かもしれない。それでもいいのだが、ここはもう少し、小津が「もののあはれ」という言葉を発した昭和二十六年(一九五一)に留まることにしたい。小津にとっては「麦秋」の年であり、サンフランシスコ講和条約が締結され、全面講和ではなく、単独講和(多数講和)によって国際秩序への復帰が決まった年である。占領の終わりは近づいていた。」(132頁)
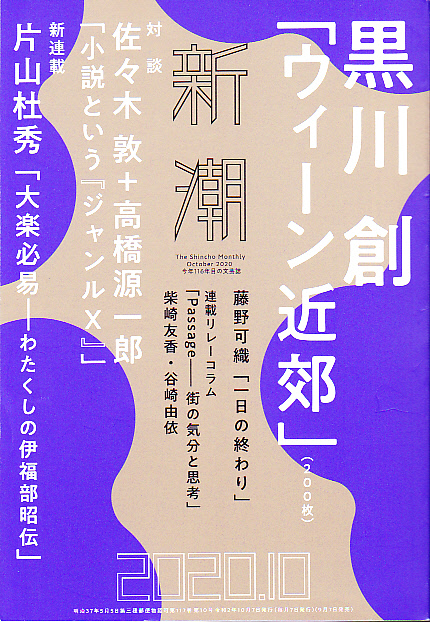
帯「無の美学から日常の政治性へ 小津は保守的で日本的なのか。だとしても、それはどういう意味でか。映画産業との関係を含め、大不況や戦争、復興など、近代性と葛藤する同時代の日本の歴史的文脈のなか、それをせめぎ合う作品を精緻に読み解き、新たな小津像を提示した国際的力作。」
序章(1-28頁)
小津、歴史、日常(1-4頁)
日常を研究する(4-15頁)
日常と日本の近代(15-20頁)
小津研究における方法-テクストと文脈(20-28頁)
第一章 初期の小津-小市民映画と日常的リアリズム(29-77頁)
松竹の誕生-小山内と野村(32-36頁)
蒲田調と日常のリアリズム(36-49頁)
日本の中産階級と小津の小市民映画(49-67頁)
日常における逸脱(67-77頁)
第二章 過渡期における小津-サウンド版とファミリー・メロドラマ(79-185頁)
小津とトーキー(81-92頁)
喜八もの-ノスタルジックな世界への/からの旅(92-108頁)
共感における連帯-小津の女性映画(109-134頁)
第三章 戦時期の小津-ブルジョワ・ドラマと国策映画の間で(135-185頁)
軍国主義との妥協-大船と小津の戦時期(137-153頁)
ブルジョワ婦人と日常のジェンダー・ポリティクス(154-169頁)
不在の父と小津のヒューマニズム的戦争ドラマ(169-185頁)
第四章 戦後の小津-占領期の小津映画と復興された東京(187-243頁)
戦争、戦後、近代(189-201頁)
占領期の小津映画における日常とジェンダー関係(201-219頁)
一つの都市の二つの物語-復興された東京と失われた東京(219-243頁)
第五章 晩年の小津-新世代と新サラリーマン映画(245-274頁)
新世代(246-262頁)
新生活(262-274頁)
終章(275-283頁)
注(285-317頁)
あとがき(319-324頁)
参考文献(11-24頁)
図表一覧(8-10頁)
索引(1-7頁)

平山周吉「小津安二郎 第四回 第四章 「麦秋」の空、「麦秋」のオルゴール」(302-312頁)
※冒頭を引用する。
「小津映画唯一のクレーン撮影は「麦秋」のラスト近くにある。原節子と三宅邦子が起伏のある砂丘をゆっくりと並んで歩く後ろ姿をクレーンは静かに追っていく。その撮影には三日もかかったと厚田雄春キャメラマンは、蓮實重彦の質問に答えている。「移動する時も必ずご自分でファインダーを見られるので考えてる様にならない。クレーンの操作は数人で動かすので監督の視点に入らない、それで何回やっても安定する個所にきません。(略)で、三日間クレーン撮影に時間をかけようやくOKでしたが、ご機嫌が悪かったです。(略)下が砂なんでクレーン揺れないように下にいろいろ敷いて[キャメラは原と三宅に]まっすぐ近づいて、ゆっくり上るのです。だからクレーン使っても俯瞰じゃないんです」(蓮實『監督 小津安二郎』付録インタビュー)」(302頁)

主催:江東区文化コミュニティ財団、江東区古石場文化センター
会場:江東区古石場文化センター
12月12日(土)東京物語
12月13日(日)麦秋
上映前特別講演会「麦秋と原節子」(築山秀夫:全国小津安二郎ネットワーク副会長・長野県立大学教授)
12月13日(日)ギャラリートーク&解説「特別展・築山秀夫コレクション展 原節子と小津映画-原節子生誕100年記念-」


平山周吉「小津安二郎 第五回 第五章 「大和はええぞ、まほろばじゃ」(266-276頁)
※冒頭を引用する。
「昭和二十六(一九五一)十月三日に封切られた「麦秋」の同時代評を読んでいると、「麦秋」に強く影を落とす戦争について、言及されることが少ない。「南方での戦死」、「徐州戦」、「尋ね人の時間」など、それとわかる話題がセリフに出てくるのに、もっぱら鎌倉での中流の生活、二十八歳の原節子の縁談にばかり興味が向かっている。戦争の傷跡はまだまだ残っていても、戦後を生きる日本人の関心は目の前のことに集中してしまっていたのだろうか。「麦秋」の登場人物には、「空」を見る人物と、「空」を見ない(あるいは見ることを忘れた)人物がいると前章で指摘した。前者の代表が菅井一郎・東山千栄子の老夫婦であり、後者の代表が長男の笠智衆と悪ガキ兄弟である。原節子は戦死した次男・省二の親友だった二本柳寛との結婚を自分で決めることで、前者に属すことを無言で決断する。昭和二十八年(一九五三)の「東京物語」では、その原節子は戦争未亡人役だが、最後のほうで亡き夫のことを、「でもこのごろ、思い出さない日さえあるんです。忘れてる日が多いんです」と告白する。忘れることがむしろ自然なのだと、小津は苦く観念したのだろう。」(266頁)
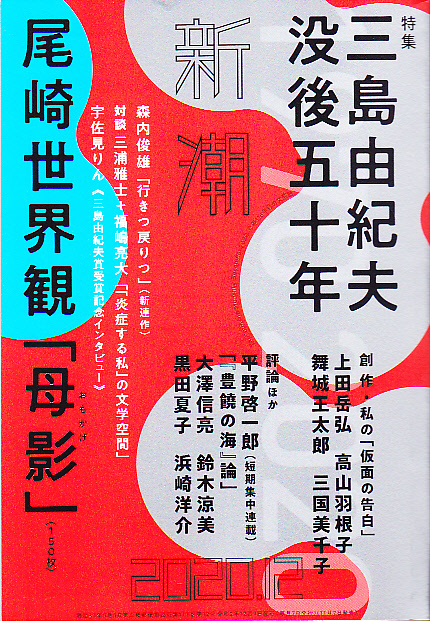
このホームページ内のテキスト・画像の無断使用はご遠慮下さい。