及川満「小津安二郎論・序説 晩年の諸作品(1)」(83-96頁)
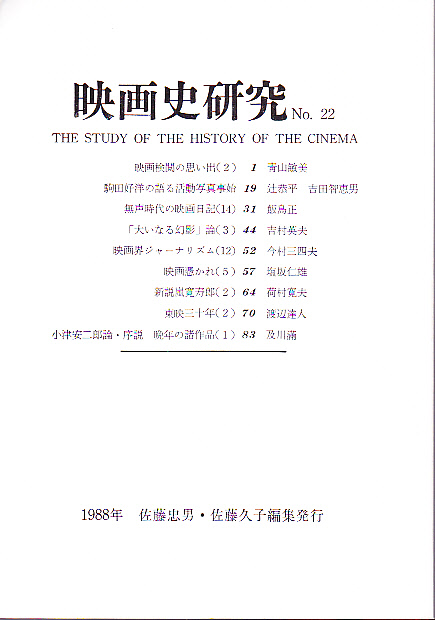
「厚田雄春インタヴュー 小津安二郎と松竹蒲田撮影所」(聞き手:蓮實重彦)(8―15頁)

「厚田雄春インタヴュー 露出計なんて高嶺の花でしたね」(聞き手:蓮實重彦)(22―29頁)
※グラビア「戦後、帰国して間もない頃、京都の清水宏を訪ねた小津安二郎」

「小津安二郎」(174―188頁)

「日本映画の至宝 小津安二郎」(11-
写真「ゴザの上に腹這いになってカメラ位置を決める小津安二郎監督(『浮草』から)。」
◇年に一度の小津まつり(12-14頁)
「小津は、常連のベテランで、毎度おなじみのようなシーンから撮影を始めるのである。「笠さんの前のお銚子、もうちょい海寄りだ。あっ、行きすぎた。そうそう。そこがいい。春さんの右手は、心持ち観音様側に置いて…」静まり返ったセットだから、低くて、鼻にかかった小津の声が、重みを持って、よく通る。ところが、その小津監督が、どこにいるのか、姿が見えない。声は、スタッフの人垣の中から聞こえてくる。肩越しに見ると、低い位置に置かれたカメラをかかえ、真っ白いピケ帽をかぶった大男が、銭湯の洗い台みたいな木の椅子に腰を掛けていた。大船で助監督が、唯一人「先生」と呼ぶ、神様の様な、”小津巨匠”であった。小津は、ルーペをのぞき放しで、フレーム内の小道具、人物の手の位置まで指示した。海寄りは、鎌倉寄り。観音側は大船駅の方向なのだそうだが、一ミリの狂いも許さない。」
「テスト中、カメラから目を離さない理由を小津は、後日、「オレの流儀だよ。ひとつ、ひとつの画面、ワクー絵画で言えば額縁を特別に気にするんだよ」と、説明してくれた。」
◇シンボルの純白の帽子(15-16頁)
「仕事の時、小津は、真っ白なピケ帽をかぶった。冬はグレーの背広で、カシミヤのエビ茶のマフラーを巻き襟に無造作に突っ込んだしゃれたスタイル。夏はノリのきいた真っ白なワイシャツ姿と決まっていた。「ハチ巻でもいいだ。髪が薄くなって、頭に汗をかくから、これは汗止めだよ」という、ピケ帽は、いつも真っ白だった。「一ダース同じものを持っていて、クリーニング屋に出して、毎朝、替えてくる」という話をスタッフから聞いた。こういうのを本当のおしゃれ、粋というのだろう。仕事着のスタイルも、小津映画そのままだということに気がついたのは、小津サンが亡くなってからである。小津は、セット撮影の日は、白タビにゾウリ愛用だった。当時は、白タビは、”ワンマン”の象徴(吉田茂首相の白タビが有名だった)なので、なんとなくおかしかった。もう一つ、小津らしい、おしゃれのワンポイントに、ボクの目は吸い寄せられた。この人は、ズボンのベルト代わりに、女の人の帯ひもをしめていた。粋人でなくては、似合わないおしゃれだが、小津がやっている分には、少しもおかしくなかった。一見、渋くて、なんのヘンテツもないような格好に見せながら、小津は、やっぱり粋で、通人だった。」
◇短いセリフほど時間がかかる(16-19頁)
「小津映画には、よく「ああ、そう」「そうかい」「ふうん」といった短いセリフがある。脚本をみると、こんなのは簡単と思いがちだが、小津の演出では、こういった短いセリフほど、簡単にはすまなかった。『彼岸花』では、高橋貞二が「ピーナッツ、ピーナッツ」というだけのセリフで、テスト40回の記録を作った。例によって「もう一回」「ハイ、もう一度」小津は、高橋のいい方が気に入らず、自分で「ピーナッツ、ピーナッツ」と、言ってみせた。「なじみの客なんだ。”ピーナッツが出てねェゾ”というセリフがあるつもりで言えよ。”ピーナッツ売り”じゃないんだから。」「だいぶ調子が出てきた。もう一回、やってみよう」「…また、悪くなった。十三回目にやったのが、一番よかった。あの調子を思い出して、もう一回」
「小津演出は、ベテランの芸達者にも、「紅茶をスプーンで二回半、右回しで、かき回して、顔をあげてから、セリフを言ってください。」なんて注文を付けた。涙のシーンでは、巨匠が自分で、女優の目の下にワセリンを綿棒で塗ったりした。俳優もオブジェであった。演出中の小津は、決して威張ったり、声を荒げたり、怒鳴ったりはしなかった。それどころか、よく冗談や、皮肉をいった(みんな緊張して、あまり笑わなかったが)。肩幅の広い、大船きっての偉丈夫。立派な鼻、口ひげ、像のような目に微笑をたたえた巨匠の風格、威厳に圧倒されて、みんなすくんだ。」
◇トンネルを抜けると仙人境(20-23頁)
「それよりも僕は、日常生活で、トンネルを抜ける歩数までキッチリと決めているのかー小津らしいな、と、演出を思い浮かべて、妙に感心してしまった。」「小津は、僕が日刊スポーツ新聞社で、杉戸豊君と同期の記者だということを知っていて、「豊ちゃんは、元気でやっているかい?」と聞いた。豊ちゃんとは、小津のお気に入りだった佐田啓二夫人(中井麻素子さん)の弟である。この日の小津は、機嫌よく、ぶしつけな質問にも、ニコニコ答えてくれた。「中学生の頃は、映画を見に行って捕まると停学だったがね。鳥打帽かぶって潜り込んで、ダグラス・フェアバンクスやパール・ホワイトにうつつをぬかしたものさ。もともと勉学の志なんてなかったから監督になったんだが、映画に入るなんて、当時は道楽者呼ばわりされてね。堕落したみたいに思われたんだよ」
◇ゴザ係でロケハン同行(23-25頁)
◇一番乗りをするんだと!(25-26頁)
「小津の愛唱歌は「シンガポール攻略の歌」だった。酔いが回ると、一番乗りをするんだと笑って死んだ戦友のオーと歌った。戦時中も、軍に協力する映画をついに撮らなかった小津が、軍歌を?とメクジラたてることはない。シンガポールで、次回作準備中で終戦を迎えた小津。映画界の賞という賞を取り尽くし、映画界で初めて芸術院会員に選ばれた受賞祝賀会の二次会でも、亡くなったあとの「小津忌」でも、この歌は”小津組の歌”として歌われた。」

「Ⅰ 映画からの解放-小津安二郎『麦秋』を見る」(5-72頁)
「Ⅱ 内なる制度と戯れる」(73-90頁)
石原開「解放としての倒錯性」(91-101頁)
※1987年6月に、河合塾千種校での講演をもとに作成された。
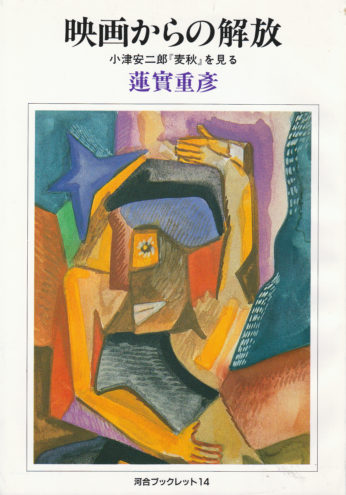
「小津への敬意が作品を生む ヴィム・ヴェンダース『東京画』」(128-131頁)
「ベストワン1985年 フランク・ボーゼージ『第七天国』」(144-147頁)
「東京を映し出す二本の映画」(179-181頁)
「真実と現実を<わたし>に伝えるヴェンダースの声」(182-186頁)
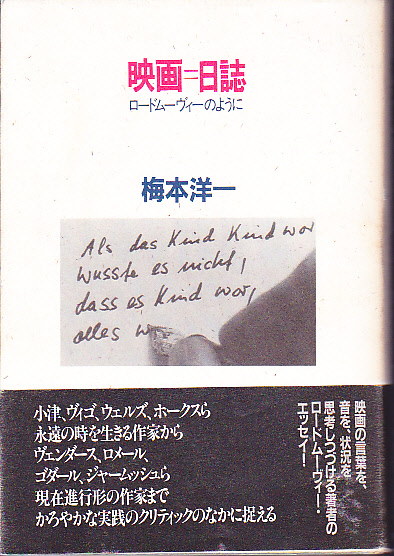
「小津安二郎 書簡(昭和二年十月三日)-映画的文体-」(122-124頁)
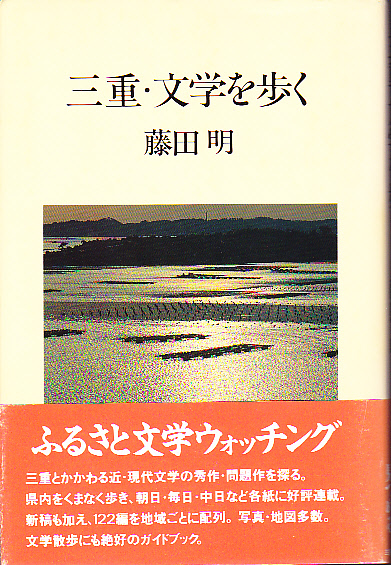
このホームページ内のテキスト・画像の無断使用はご遠慮下さい。