「YASUJIRO OZU」(69―98頁)
「Movie Mania」(72―73頁)
「From “Nonsense” to social Realism」(73―77頁)
「The Human Order」(78―81頁)
「Looking Up and Beyond」(81―84頁)
「Tokyo Story」(84―87頁)
「Target for Iconoclasts」(87―88頁)
「Notes」(88―89頁)
「YASUJIRO OZU:Filmograohy」(90―98頁)
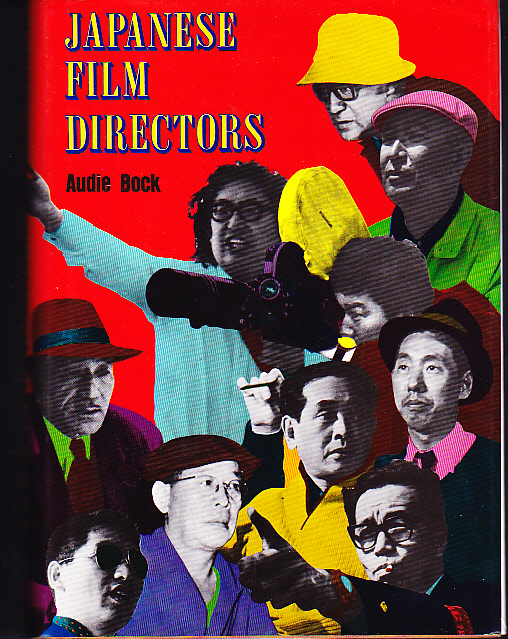
及川満「小津安二郎論・序説(6)第二章「早春」の頃(続き)」(46-91頁)
TADAO SATO「THE ART OF YASUJIRO OZU (8)」(91-96頁)
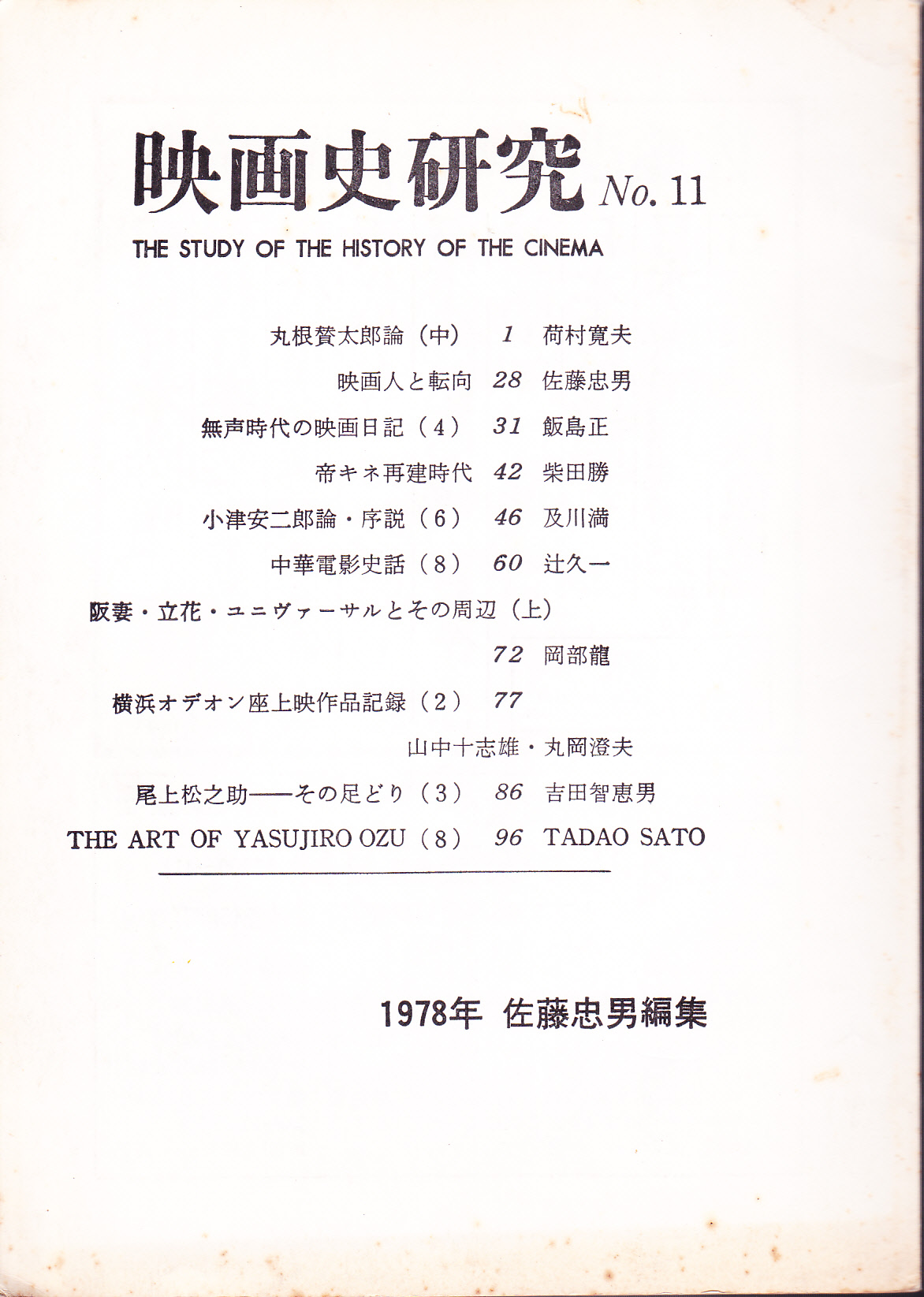
及川満「小津安二郎論・序説(7)」(82-91頁)
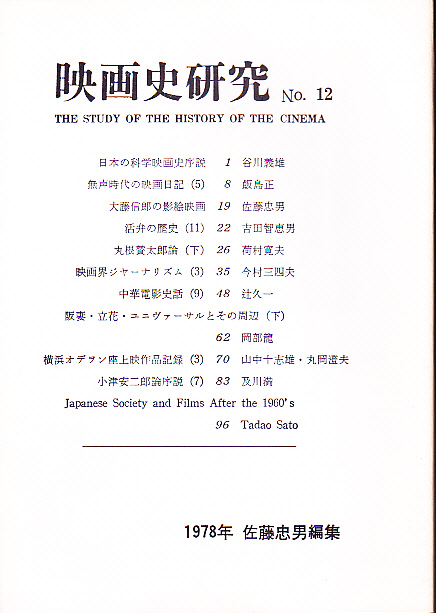
「長屋紳士録」(14頁)
「風の中の牝鶏」(15―16頁)
「6 観照的な様式 大船調の至高・小津安二郎」(161―185頁)
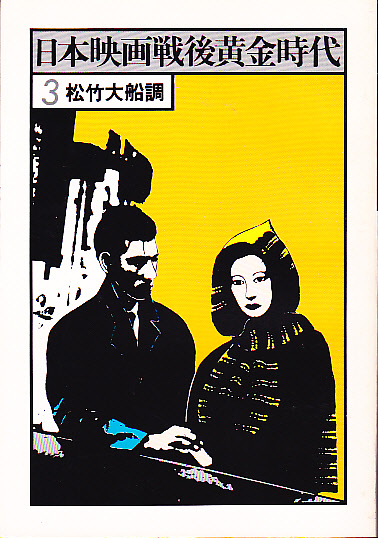
「ポスター お早よう」(1頁)
「7特別招待席の巨匠たち 小津安二郎」(182―184頁)
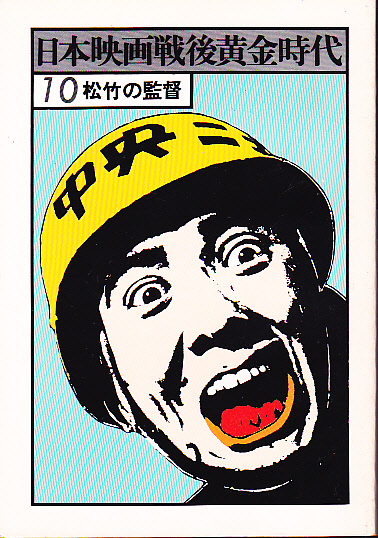
Hubert Niogret 「Introducing:Yasujiro Ozu」(2-12頁)
Robin Wood「Voyage a Tokyo」(13‐16頁)
Yasujiro Ozu「Pour parler de mes fims」(17-25頁)
Chishu Ryu「Yasujiro Ozu」(26-27頁)
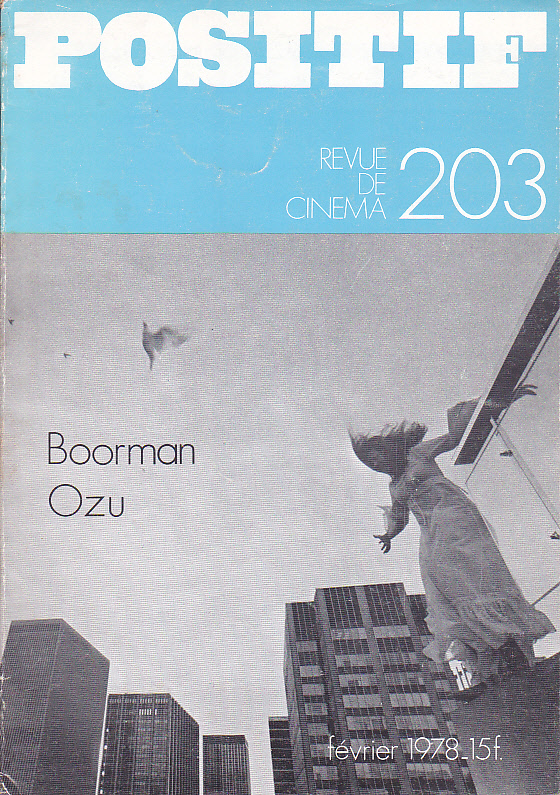

「日本映画への視線-アンケート’66」(147-156頁)
※当時のヌーヴェル・ヴァーグの小津評を知ることができる貴重なアンケートである。例えば、アラン・レネは次のように答えている。「パリで見られる日本映画の数はたかが知れたもので、なぜもっと見れないものかと腹立たしいくらいである。その数少ない日本映画のうち、私の心に最も深く残っているものは、まず『東京物語』、『早春』、『一人息子』、『東京の合唱』などの小津安二郎の諸作品である。小津作品の魅力を一言でいうのは不可能だが、少なくとも、彼の作品のほとんどの音楽的なリズム感は全くユニークなものだ。全てが静のようにみえながら、実は全てが確実な生命の躍動感に息づいている。セリフ、そして人物の目のまばたき、手の動き‥それら全ての些細なジェスチャーは、作品全体の旋律を構成する一つ一つの音符のような感じがする。私の作品の中で、『ミュリエル』(1963年)の画面構成に最も大きな示唆を与えてくれたのは小津作品である。」(154-155頁)
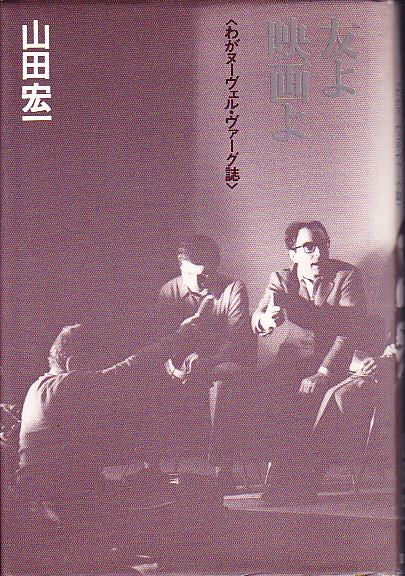
「Filmographie succinte de Yasujiro Ozu」(4頁)
Max Tessier「Le temps s’est arrete」(5頁)
Max Tessier「Entreitien avec Chishu Ryu」(6頁)
「VOYAGE A TOKYO」(7-61頁)
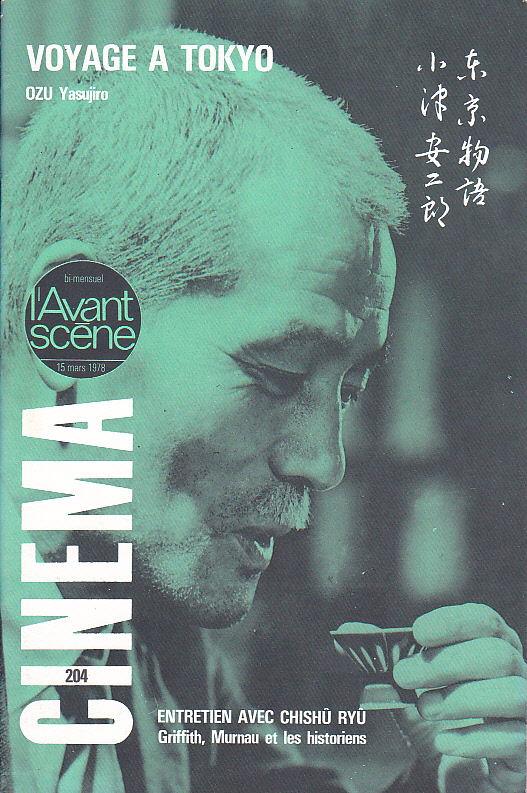
michel ciment「sous les yeux de loccident ( ozu et la critique anglo-saxonne 1957-1977)」(30-36頁)
eithne bourget「les rites de la communication et du silence」(37-39頁)
hubert niogret「biofilmographie de yasujiro ozu」(40-44頁)
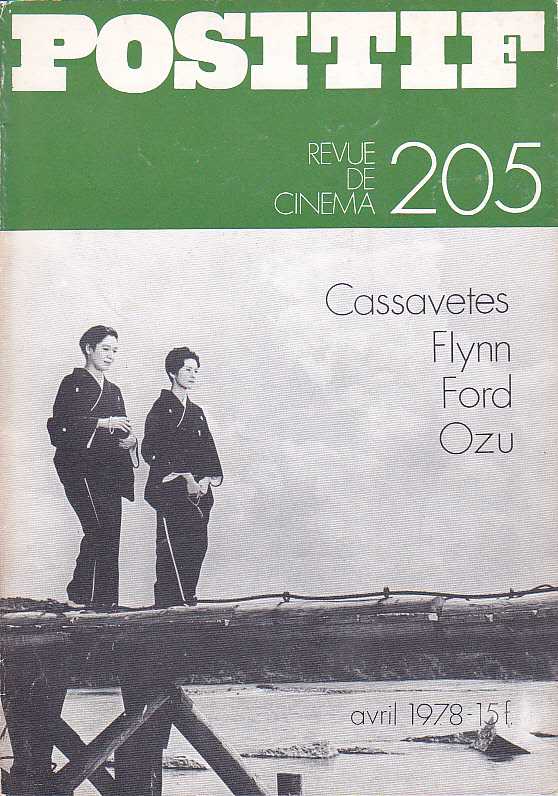
はしがき(7-13頁)
序章(17-37頁)
第一章=脚本(39-152頁)
第二章=撮影(153-223頁)
第三章=編集(225-262頁)
終章=結論(263-270頁)
伝記と作品目録(271-357頁)
訳注(358-370頁)
参考資料(371-377頁)
謝辞(378-379頁)
訳者あとがき(380-385頁)
索引(386-397頁)
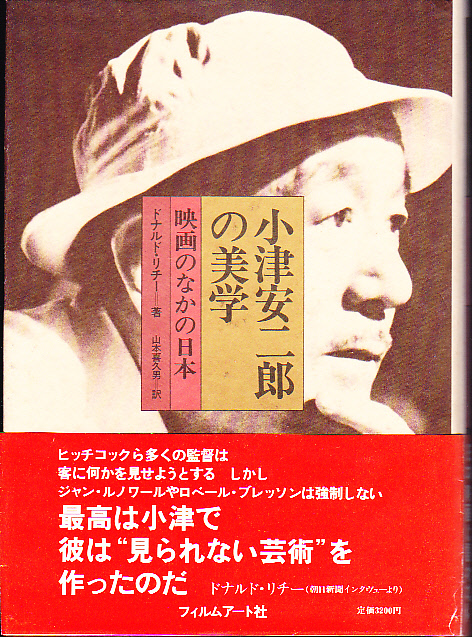
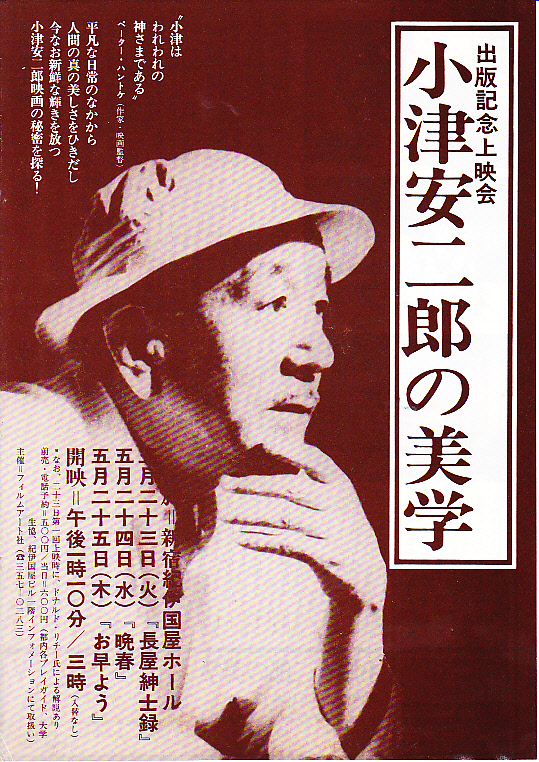
蓮實重彦「『無』のフィルム的生産、その過剰と欠如ー小津安二郎論」(234-251頁)
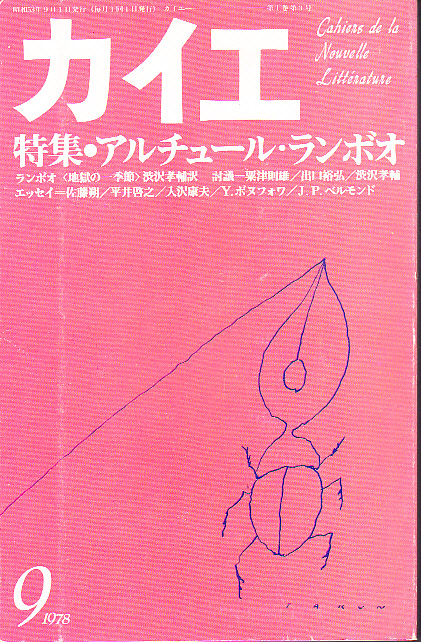
「LE GOUT DE SAKE, FIN D’AUTOMNE Yasujiro Ozu」(74-75頁)
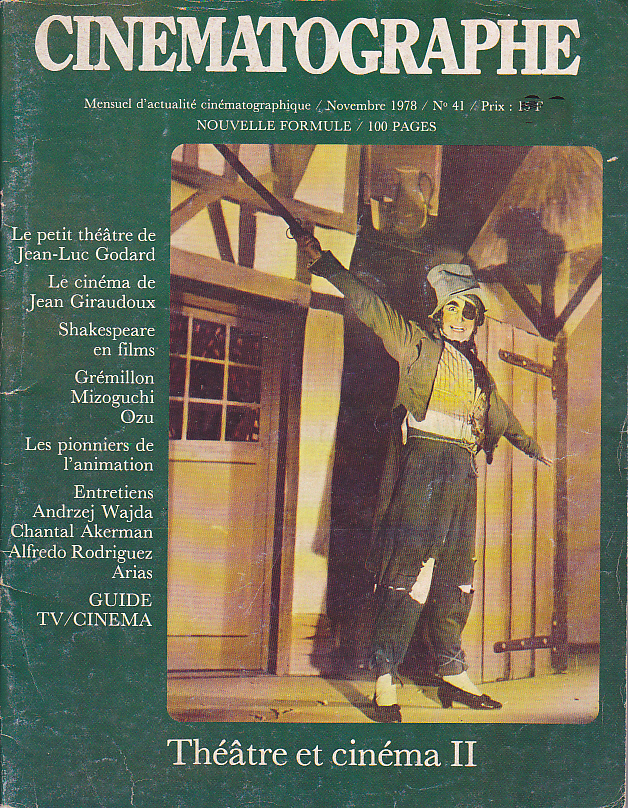
Don Wills「Yasujiro OZU Emotion and Contemplation」(44-49頁)
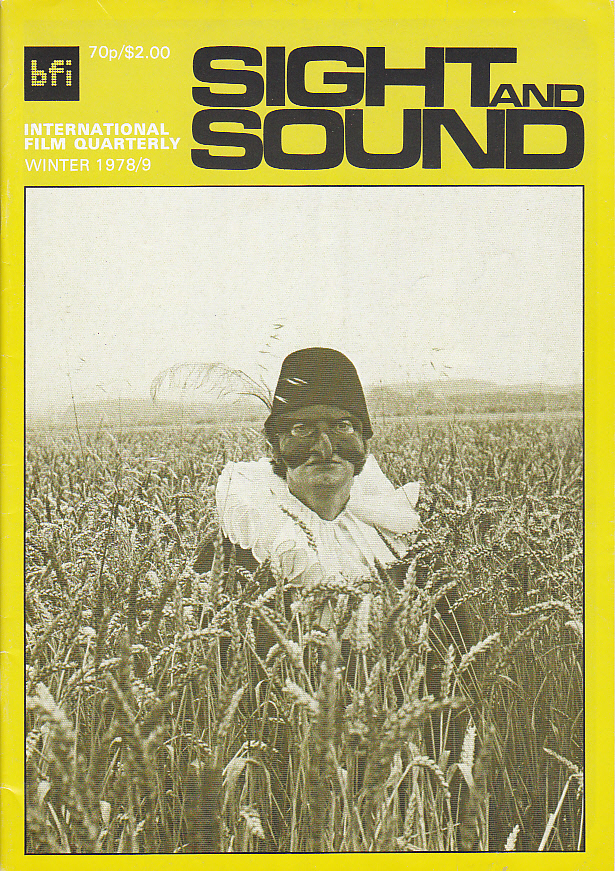
このホームページ内のテキスト・画像の無断使用はご遠慮下さい。