「ジャンプ’63 映画監督小津安二郎 自宅客間(鎌倉)」(7頁)
※撮影企画によれば、明治以降の日本が迎えた卯年は、いつも危機感に満たされた年であった。そこで、それ以前の卯年のようにならないように、むしろうさぎが大きく跳躍できるような年にしたいと願い、このグラビア企画を練った(94―95頁)とある。そして、109人がジャンプし、67枚の写真が掲載された。巻頭は、衆議院議長清瀬一郎。続いて、東大総長茅誠司、東本願寺裏方大谷智子、奈良女子大教授岡潔、柔道銃弾三船久蔵、作家獅子文六、画家前田青邨に続いて、7頁目に小津監督が掲載されている。実は、この企画にはモデルがある。フィリップ・ハルスマンの『JUMP BOOK』(1959年)という写真集。アメリカの高名な政治家、実業家、学者、芸術家、俳優、女優など、例えば、ニクソン大統領やサルバドール・ダリ、マリリン・モンローなど各界の大物たちがジャンプする姿178点が収められている。小津監督の写真撮影エピソードについて、「小津監督は、二年前、野球をやっている時にアキレス腱を切ったことがあるよしで『飛べるかな』と言いながらも、軽くポンポン飛ばれました。小津監督の十八番である低い角度からの写真ですが、お気に召しましたでしょうか」(97頁)と結んでいる。

日本映画史に燦然たる、不滅の金字塔を打ち樹てた、名匠・小津安二郎監督、30余年の足跡!
代表作品場面集、小津安二郎監督の略歴

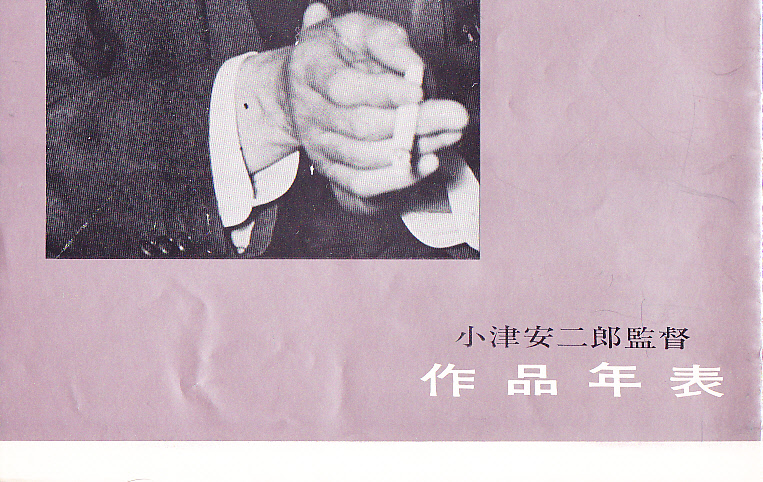
「巨匠最良の日 芸術院会員/小津安二郎を祝う会」(18―19頁)
「岡田茉莉子、小津安二郎、若尾文子」、「中井貴恵ちゃんと小津監督」4ショット
※一部抜粋する。「映画界で初めて芸術院会員となった小津安二郎監督を祝う会が、二月十三日夜、東京赤坂のホテル・オオクラで開かれた。これは日頃、小津氏となじみ深い先輩、友人、門下生などが発起人となってお祝いしたもの―永田大映社長、城戸松竹社長、シナリオライター野田高梧、作家久保田万太郎氏はじめ、笠智衆、佐田啓二、岡田茉莉子、若尾文子、佐久間良子、鰐淵晴子らかけつけた参会者は約五百名」

「対談 小津安二郎・岩下志麻 先生どうして結婚なさらないの
六十を迎えてなお独身の小津安二郎監督に岩下志麻さんが聞く独身の秘密
早春のあたたかい陽射しのふりそそぐここ北鎌倉の小津監督邸の庭先で、結婚について語り合う小津監督と岩下志麻さん」(144-147頁)

小津安二郎「映画セットで思うこと」(70-71頁)
冒頭を引用する。
「時価何百万円もするという絵をむりして借り、その日の撮影が済むと銀行にあずける。昔だったらそれほど高価なものを借りないでも、美術部のものが泥絵具かなんかでごまかした所だったが、近頃は観客の眼が肥えてきたから、ほんの数秒のシーンのためとはいえ、やっぱり本物をつかわなければならない。あまり長い間ライトに輝らすので油がとけてくるうではないかとまで心配しながら。」
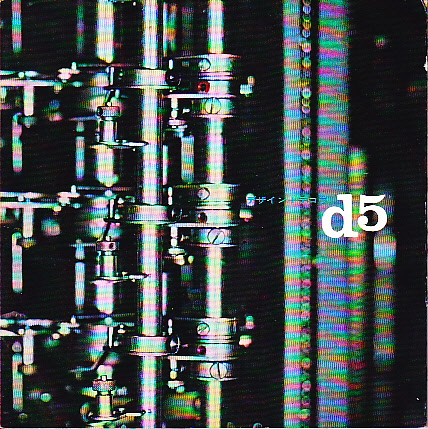
表紙:小津安二郎 裏表紙:溝口健二
「I Was Born,But‥」「Tokyo Story」(2頁)
「Late Autumn」(3頁)
「Late Spring」(4頁)
「Early Spring」「Good Morning!」(5頁)
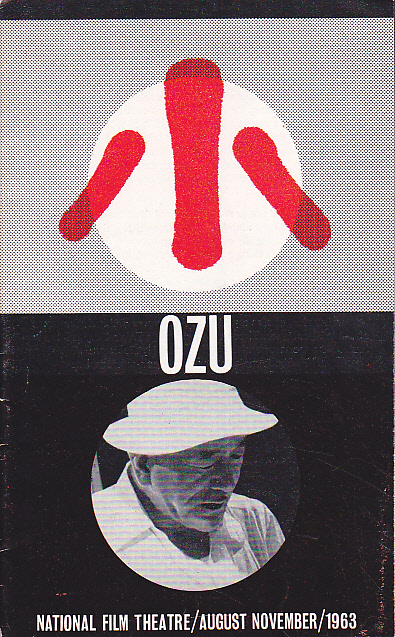
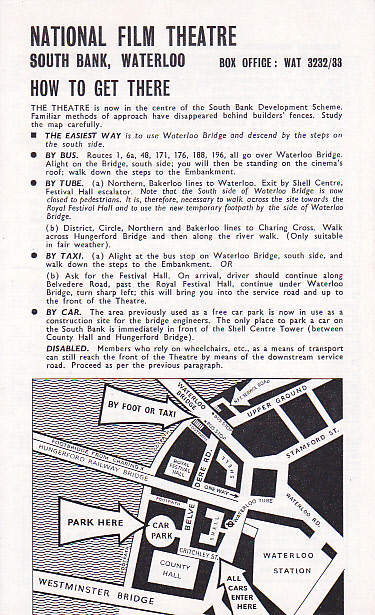
表紙:カレン・スティール
「ベルリンの小津安二郎映画」(45-46頁)
ベルリン映画祭で話題をよんだ小津安二郎作品展の模様を現地からドナルド・リチィ氏の報告を中心にさぐる
※冒頭を引用する。
第十三回ベルリン国際映画祭は、あまり成功とはいえなかった。現地の新聞クルフルシュテンダム紙は今度の映画祭について「ベルリン映画祭をなぜフィルム・フェアとよぶことにしないのだろう-しばらく前から既にフェスティバルではなくなっているのに‥」と書いた。
映画の商談も低調だったようだし、映画祭に参加したミケランジェロ・アントニオーニやスーザン・コーナーといった人たちも、一日か二日いただけで他のもっともしろい場所に行ってしまった。
だがそれだけに、こんな状態の中で、日本以外にはほとんど知られていない小津安二郎の映画が六本が上映されたことは、おおきな効果を生み出した。その六本の映画とは、昭和七年に作られたサイレント映画「生まれてはみたけれど」と戦後の「晩春」「東京物語」「早春」「お早よう」「秋日和」である。このうちヨーロッパで上映されたことのあるのは「東京物語」だけで、この作品はパリ・シネマテイクの世界映画ベスト・テンに入っている。
この作品展のプランをたてて上映前の解説者の役をつとめサイレントの「生まれてはみたけれど」上映の際はピアノ伴奏までやってのけたドナルド・リチィ氏も、アントニオーニ作品についで難しいという世評もある小津映画が、どんな反応をヨーロッパの観客の間にひきおこすかについては、多少の懸念がなくはなかったようだ。
しかし、六つの作品上映中に席を立ったものは一人としていなかったし、だれ一人眠った者もなかった。そして笑いをよぶ場面では間違いなく笑い声がわきおこり、「晩春」と「東京物語」のラスト・シーンではあらゆる観客が涙を浮かべた。
一作品一日に外の上映が終わるたびに、観客は立ち上がって盛んな拍手を送った。映画祭の作品展では、今まであまり例のなかったことである。そして評判は口づたえにひろまり、会場はぎっしり人で埋まった。
西ドイツ最大の新聞ディ・ヴェルト紙は、「今年のベルリン映画祭は無駄になるところだったが、オヅ作品展がそれを救ってくれた」と書いたし、ミュンヘンとハンブルクの新聞は小津安二郎についての長文の記事を載せ、ラジオ・ベルリンでヴェルナー・シュヴァイルという評論家は、「オヅ監督は今年の映画祭で真に観客を感動させた。偽りのない作品こそが、ドイツにあっても、日本にあっても、批評家からも一般のひとびとからも迎えられるものである」と放送した。
なかでも、もっとも強い影響をこの作品展から受けたのは、若い映画批評家や若い監督たちである。「今、正解には、まったくユニークな映画のスタイルが二つある。一つはアントニオーニ、もう一つはオヅだ」と、カイエ・デ・シネマの若い記者は言った。「オヅはカール・ドワイエルそっくりだ。自分の描きたいものを描くただ一つの方法を彼は心得ている」という意見もあった。

登川直樹「各部門の流れ 映画部門」(146-151頁)
一部を紹介する。「昭和26年の「麦秋」以来しばしば芸術祭賞を受けた小津安二郎監督は、秋の封切に予定されると、真夏の撮影にはいちばん能率の悪い時期に仕事をしなければならないので閉口だが、いつもそうなってしまったと語っている。こういう感慨は芸術祭参加作品と取り組んだ制作スタッフの誰もが味わったにちがいない。」(147頁)
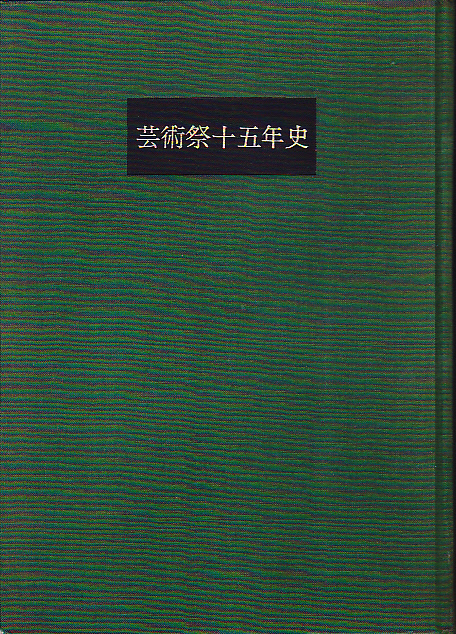
毎日名画鑑賞会第35回招待券『秋刀魚の味』
主催:毎日新聞開発KK
後援:スポーツニッポン新聞社

「小早川家の秋」鎌倉文士試写会
小津安二郎監督の「小早川家の秋」を見る会が、10月23日、鎌倉の市民座で開かれ、鎌倉文士など多数が観賞した。

「庶民とともに 小津安二郎逝く 哀しみのなかに恩師をしのぶ”小津学校”の生徒たち」
ペーソスあふれる庶民の生活を描いての第一人者、小津安二郎監督”松竹”は12月12日、頸部悪性腫瘍で死去。慈愛の人、小津さん。そのやさしい顔が忘れられないという”小津学校卒業生”たちが偲んだ言葉 そこには小津さんが歩んだ四十年の映画生活からにじみでた人生訓があり、私たちの心に深い感銘を与えずにはおかないものがある。
貴恵ちゃんの祈りもむなし(156頁)リンゴとバナナとカキの話(157頁)「やさしさときびしさと‥」「ラーメンお茶漬の人生哲学」(158頁)

「今週のハイライト 巨匠逝く/ありし日の小津さん」(18―19頁)
※「日本映画界の最長老である小津安二郎監督が十二月十二日午後零時四十三分、頸部悪性シュヨウのため、入院中の東京医科歯科大附属病院で死去した。小津氏は大正十二年松竹蒲田撮影所に入社、昭和二年『懺悔の刃』で監督になり、以来サイレント、トーキー時代を通じて、『戸田家の兄妹』、『晩春』、『麦秋』、『彼岸花』、『秋日和』など多数の名作を発表したが、昨秋の『秋刀魚の味』が遺作になった。同監督の作品は格調高いリアリズムを守り、”小津調”とうたわれた―この秘蔵写真はよき酒徒であった同氏が佐田啓二邸でおどけたときのものである。」(18頁)

「小津監督のガールフレンド」38頁
映画人として初めて芸術院の会員に選ばれた小津安二郎氏を祝う会が二月十三日夜、東京赤坂のホテル・オークラで開かれた。この夜、小津氏を祝って集まった人々は、永田雅一、城戸四郎、大仏次郎、井上靖、岩田専太郎、生沢朗、笠智衆氏ら五百人。小津映画の常連佐田啓二さんの司会で、祝賀会は進められたが、この会の発起人を代表して、菅原通済氏は、「万歳を叫びたい気持ちでいっぱいです。この次はぜひ文化勲章を」。
※ガールフレンドとは、佐賀啓二さんのお嬢さん貴恵ちゃんのこと

表紙:水上勉、池田勇人、山本富士子、長嶋茂雄、江利チエミ、故ケネディ米大統領、依田郁子、海老原博幸、坂本九
「おやじ小津安二郎はもういない(佐田啓二の看護日誌)」(12―17頁)
※見出しのみを拾う。「ガンでなくなった大監督の最後の企画はガンに苦しむ人の物語だった」、「ハレモノを退治するまでは」、「首に針を入れ一週間」、「ガンをテーマの『大根と人参』」、「吸いのみにブランデー一滴」、「苦痛の声が玄関にも」、「”およめさんもらえばよかったよ”」、「柩は山道のもみじを踏んで」

「ニュースあらかると 文化 最後の日本的監督の死 「お茶漬の味」を守った小津安二郎氏」
※冒頭を引用する。
しばしば重体を伝えられていた小津安二郎氏が、さる十二月十二日、とうとうなくなった。頸部悪性シュヨウ、つまりガン。長い間痛さに苦しみ、弱気になり、ちょうど満六十歳を迎えた誕生日に、死がやってきたのである。生涯めとらず(原節子とのロマンスはうわさされたが)、母親ま(ママ)さえとの二人暮らしだった。そのま(ママ)さえさんが昨年二月に亡くなり、年の暮れに映画界から初の芸術院会員に選ばれた時、「母が生きていたら」といったが、こんどの重病では「老母をあとに残さないでよかった」ともらしたそうだ。終始、日本的な親子の情を描き続けた小津さんらしい話である。

このホームページ内のテキスト・画像の無断使用はご遠慮下さい。